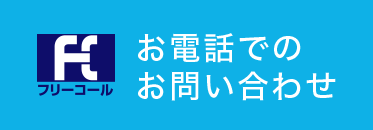『産業看護職』なぜ必要?
弊社では健康経営に関するサービスをワンストップで提供しておりますが
産業看護職の皆様へお仕事のご紹介やリカレント教育の一環としてセミナー開催にも力を入れております。
私たちは、産業医はもちろん
産業看護職の皆様の活躍こそが健康経営の普及に必要であると考えております。
そこで、今回は産業看護職がなぜ必要なのか?についてお伝えいたします。
産業医と産業看護職の選任義務
常時雇用する従業員が50名以上の事業場では産業医を選任することが法律で義務付けられていることは
ご存知の方も多いのではないでしょうか。
従業員50名~3,000名であれば1名以上、3,0001名以上であれば2名以上選任することが定められています。
また、「嘱託産業医」や「専属産業医」という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃると思いますが
事業場の従業員が1,000名以上の場合、嘱託産業医ではなく、専属産業医を選任する必要があるというのもポイントです。
上記のように、産業医に関しては法令で定められている一方で産業看護職はどうでしょうか。
産業看護職の選任は2025年3月時点では法令化されておりません。
しかし、前述した通り従業員の健康増進、そして健康経営の推進には
産業看護職の活躍が不可欠であるとプライマリー・アシストは考えております。
そこで、次でそのように考える理由をお伝えしたいと思います。
産業看護職の強み
そもそも、世の中にはどれくらいの企業があるかご存知でしょうか。
総務省統計局による令和3年の調査によると、令和3年6月1日時点で約368万社の企業があるそうです。
(我が国の事業所・企業の経済活動の状況~令和3年経済センサス‐活動調査の結果から~/総務省統計局)
一方で認定産業医の数はというと、死亡・失効等を除いた有効者数で約7万人となっております。
(医師会が関わる産業保健の現状/厚生労働省)
もちろん、上記の企業数には産業医選任義務のない規模の企業も含まれますが
とはいえ、産業医だけで全ての企業の健康管理を担うのは物理的に難しいというのはご想像頂けるかと思います。
企業を担当している産業医であっても、月1~2回の非常勤勤務の方が多い為
なかなか健康管理の細かいところまで入り込み予防活動に専念するのは難しいというのが現状です。
勤務日数や頻度が少なく、特に近年はメンタル不調者の数も増加しているため
その面談対応に追われてしまうという状況も多くあります。
産業看護職の場合は、産業医に比べより従業員に近い立場での細やかな対応が可能です。
企業により雇用形態に差はありますが、従業員に近い立場にいることで
ひとりひとりの体調の変化にも気付きやすく、また、従業員からの健康相談もしやすいといった効果があります。
前述の通り、産業医は時間が限られているためどうしても不調者の対応をメインに行う事が多いですが
看護職は不調者対応だけでなく未病・予防に取り組むことができ
健康経営の推進においても中心的な存在となることができるのです。
産業看護職の活躍が健康経営の推進に
現在、産業看護職を雇用している企業は大企業がほとんどです。
独立行政法人労働者健康安全機構の調査によると、99名以下の事業場でわずか4.7%。
事業場の規模が大きくなるにつれ雇用している事業場の割合も増え500~999名の事業場では47.4%と約半数。
そして1,000名以上の事業場では72.5%の事業場が産業看護職を雇用しています。
(令和2年度事業場における保健師・看護師の活動実態に関する調査報告書/独立行政法人労働者健康安全機構)
中小企業では事業場の規模から産業医の選任義務がないことが多いですが
その場合、専門的な知識を持つ産業看護職を雇用することによって
人事・労務などの企業で健康管理を担当している職種の負担も軽減するでしょう。
また、もし産業医を選任している場合にも
産業看護職は産業医との橋渡し役を担う場合も多い為、よりスムーズに連携を取っていくことが可能です。
以上のような理由から、健康経営の推進には産業看護職の活躍が必要であると私たちは考えております。